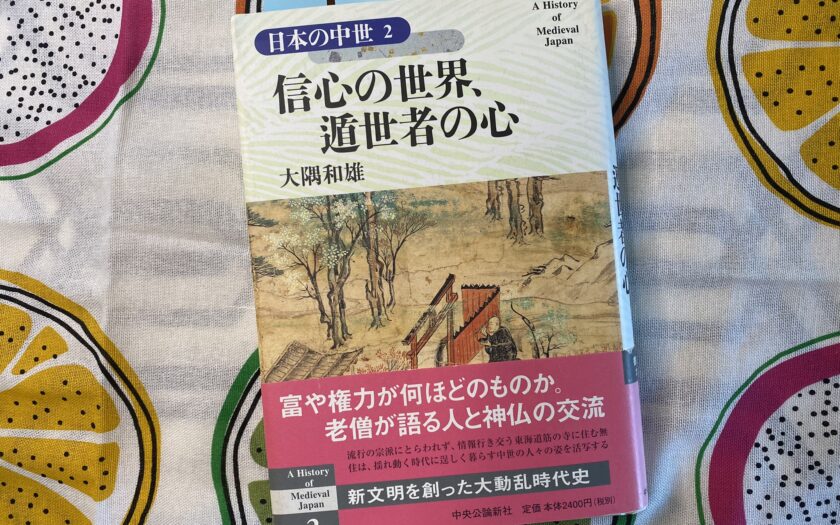「日本の中世」シリーズである。どうも、私は、「中世」と「遁世者」というキーワードに弱い。私には、「中世」が古代と近代との端境期にあたると感じられるのかもしれない。私は、もともと、「極(きわ)に立つ」とか「間に挟まれる」とか、その間にある切なさが好きで、そこから生まれる「遁世者」という生き方に憧れているのだ。どうしてなのか。ミュージックなら「J-pop」よりは水沢弘の「黒い花びら」やテレサ・テンの「つぐない」に魂が打ち震える人間だからかもしれない。それも、どうしてなのか……分かるわけがない。
人間の歴史や情報は、ある基準で残されるのだと思う。まず、その情報を記録残せる意味では、文字や文法を知っていること。まぁ、絵や象形文字でも良い。とにかく意味を伝える能力が必要である。ここでは言語は省いておくことにする。そして、次は、その情報を写す媒体、簡単に言うと「紙」「石」「木簡」などが必要である。もちろん、それを記憶する染料や墨や鋭利な石なども含まれる。日本の中世期に、その条件に合うのは、貴族か僧しかいない。つまり、私たちが知る当時の記録は、貴族か僧の視点での情報しかないのが本当である。当時の庶民の想いや考えなどが私たちの目の前に現れるのことは、ほとんどないのが現実だ。
この本は、僧でありながら遁世者でもある無住という名の人が書いた「沙石集(しゃせきしゅう)」と「雑談集(ぞうたんしゅう)」を手がかりにして、同時代の目に仏教がどのように映っていたかを見ていく内容である。当時は、鎌倉時代で多くの仏法の祖師が生まれた時代である。と、まぁ、教えられているが、その考証も、ヨーロッパの宗教改革と比較して出来上がった考え方に基づいていると、この本では説明されている。日本の近代化は、鎌倉時代の宗教改革から始まったという歴史の比較研究からの理論なのだ。当日の人々に、そんな意識があるはずがない。歴史は、さまざまに分類するために創られた、ある特定の人たちの情報操作の結果なのである。その情報のみを信じるか、それとも、多くの階層の人々の多様な情報をもって観ていくか。大事なことであると私は考えている。私は、多様な視点で情報を観ていく方を選びたいのだ。
だから、著者の大隅和雄氏が書いた中世は好きだ。もちろん、赤坂憲雄も網野善彦も大好きだ。現代の私たちに、当時の人々の思いを伝えてくれるからだ。

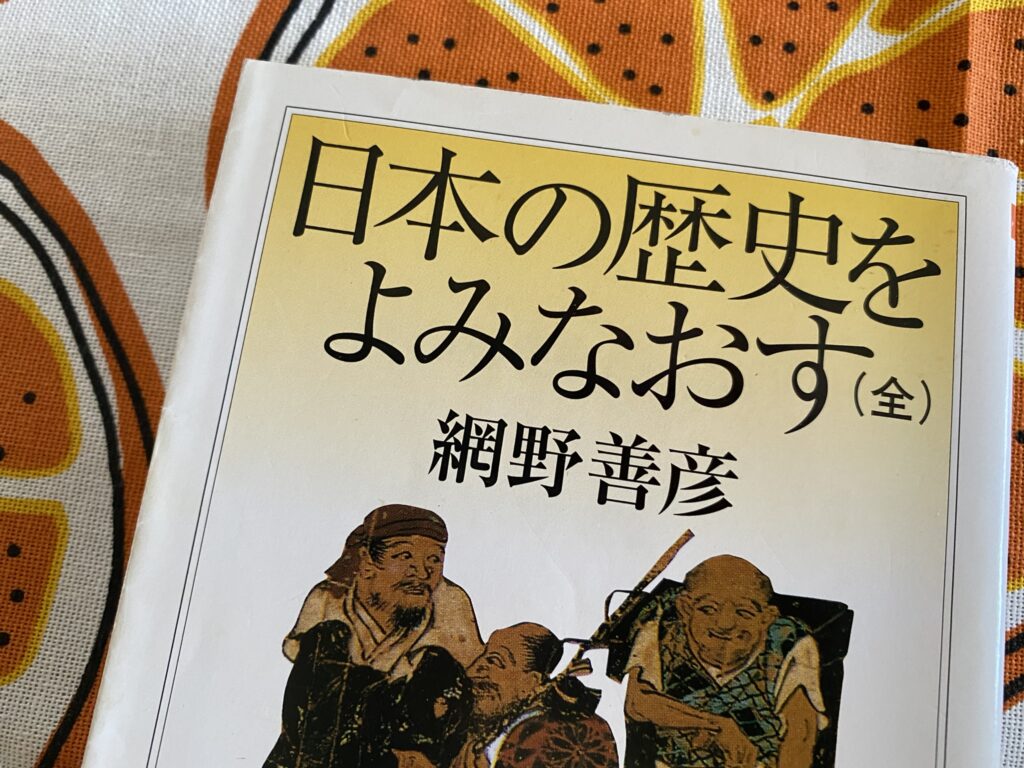
少し引用が長くなるかもしれないが、この本の特徴を覗き見したいと思う。
人間が、自分の目で見ることができるのは、ごくわずかなものにすぎない。人間は、見えない者の取り囲まれ、間に張り巡らされた見えない糸や網に捉えられて生きている。中世の人々も、見えないものに対して、いろいろ気配りし、見えないものとの関係をどのようにつけるかに、苦心しながら生きていた。見えないもののなかで、一番たいせつなものは、仏菩薩であり、八百万の神々であった。中世の人々は、諸仏諸菩薩、諸神を冥衆(みょうしゅ)と呼び、この世の中は、見えない冥衆の力によって導かれると信じていた。
遠近江国(静岡県)の伊奈佐郡奥山に、田の草という所がある。鹿や猿などの多い山里で、粟の畠を作っていたが、みな食われてしまい、収穫するものがないありさまだったので、王大夫という男が、地蔵と観音が祀られている古い堂にお参りして、両菩薩に祈念し、「今年の粟を、鹿や猿に食わせないよう、守ってくださったならば、秋には粟餅を搗いてお供えしましょう」と、軽薄にたのみごとをした。すると、本当に、王大夫の畠は、少しも鹿や猿に食い荒らされることがなく、ほかの畠はいつもの通りであった。しかし、当の王大夫は、両菩薩にお祈りしたことを忘れてしまっていた。冬になるころ、王大夫の夢に若い僧が二人現れて、「どうしたことなのか。『粟を守って、獣に食わせないようにすれば、餅を搗いて差し上げます』と言ったではないか。願いを聞き入れたのに、何のお礼もない。私を欺いたのだな」と、仰せになったところで、夢が覚めた。王大夫は、大いに驚いて、老婆に語り、急いですぐに餅を搗いて、お供えをした。また、このことを人々に語り、地頭のところへも餅を持っていって、人々にふるまった。
王大夫を見て、お供えの餅を食べた地頭の娘の尼公が語ったことである。仏は、普通の人に言うようにもの申すことがある。仏といえ心の目指す方向も、人と同じものと考えれば、応身(衆生に応じて、衆生の通りになって現れた仏)のお姿は、人と同じで、よく人を救うふるまいをなされるのである。最近起こった、不思議な出来事である。
「雑談集」より